生まれつきの持病を抱えながら育つ子どもたちにとって、医療や家族、地域のサポートは欠かせません。成長の過程で様々な困難に直面しますが、適切な支援を受けることで、自分らしい生活を送ることが少しでもできるようになることは、可能だと思います。今回は、生まれつきの病気と向き合いながら成長する子どものケースをご紹介し、支援のあり方について考えます。
事例紹介:Eくん(8歳・男の子)の場合
Eくんは、生まれつきの先天性心疾患を抱えて生まれてきました。生後すぐに手術を受け、その後も定期的な通院や服薬が欠かせません。幼少期は感染症のリスクが高く、外出も制限されることが多かったため、家族は慎重に対応されていました。
しかし、成長するにつれて「学校の友達ともっと遊びたい」「普通に体育の授業に出たい」という気持ちが強くなりました。家族や医療チームと相談しながら、Eくんが安全に学校生活を送れる方法を探ることになりました。
生まれつきの病気を抱える子どもの成長を支えるポイント
① 医療と生活のバランスを取る
- 定期的な医療ケアを受けながら成長を支える
- 小児科医・専門医との定期診察を継続。
- 体調管理や服薬管理を家族と共有しながら行う。
- 学校や地域と連携し、安全な環境を整える
- 学校と事前に相談し、体育や遠足などの参加範囲を決定。
- 看護師や保健室の先生と連携し、緊急時の対応を確認。
② 子どもの「やりたい」という気持ちを尊重する
- 病気の制限があっても楽しめる活動を見つける
- スポーツが難しい場合は、アートや音楽活動を楽しめる環境を整える。
- 体調に合わせた軽い運動(ヨガやストレッチなど)を専門家と相談しながら取り入れていく。
- 子ども自身が病気を理解し、主体的にケアに関わる
- 年齢に応じて、自分の病気や体調管理について学ぶ機会を作る。
- 服薬や病院での検査の意味を知り、無理なく向き合う習慣を育てる。
③ 家族の負担を軽減するサポートを活用する
- 訪問看護や医療ケアを取り入れる
- 定期的な訪問看護を利用し、家族だけに負担が集中しないようにする。
- 医療的ケアが必要な場合は、訪問リハビリや療育サービスも活用。
- 家族同士のつながりを持つ
- 同じ病気を抱える子どもを育てる家族との交流会やオンラインコミュニティを活用。
- 親の精神的なサポートも意識し、必要に応じてカウンセリングを受ける。
④ 公的支援・補助制度を活用する
医療的ケア児や慢性疾患を抱える子どもたちのために、以下の公的支援が利用できることがあります。
手術やリハビリ、訪問診療・看護などを必要とする場合に利用可能です。詳しくは、お住まいの自治体に問い合わせてみることをお勧めします。
小児慢性特定疾病医療費助成制度
国が指定する慢性疾患(先天性心疾患、神経難病など)の子どもに対し、医療費の自己負担額を軽減する制度。
所得に応じた自己負担上限額が設定され、長期的な治療を支援。
特別児童扶養手当
障害や慢性疾患を持つ子どもを養育する家庭に支給される手当。
病状や障害の程度に応じた金額が支給され、日常生活の支援に活用可能。
医療的ケア児支援法
2021年に施行された法律で、医療的ケア児が学校や保育園などで適切な支援を受けられるよう整備。
看護師や支援スタッフの配置を進め、通学支援を強化。
自立支援医療(育成医療・更生医療)
身体に障害のある子どもが受ける医療に対し、自己負担額を軽減する制度。
Eくんと家族の変化
Eくんと家族は、これらのサポートを活用することで以下のような変化を感じるようになりました。
- Eくんは病気と向き合いながらも、自分らしく学校生活を楽しめるようになった
- 家族の負担が分散され、無理なく介護と育児を続けられるようになった
- 学校や地域との連携により、安心して社会の中で成長していける環境が整った
まとめ
生まれつきの病気を抱える子どもたちにとって、医療的なサポートはもちろん、家庭や学校、地域の理解が不可欠です。子どもの「やりたい」という気持ちを大切にしながら、無理なく成長できる環境を整えることが大切かもしれません。
同じような悩みを抱えるご家族の方々へ、「一人で抱え込まず、支援を活用しながら一歩ずつ前に進んでいける」ということをお伝えしたいです。どんな小さなことでも、医療機関や地域の支援センターに相談してみることをおすすめします(*^^*)
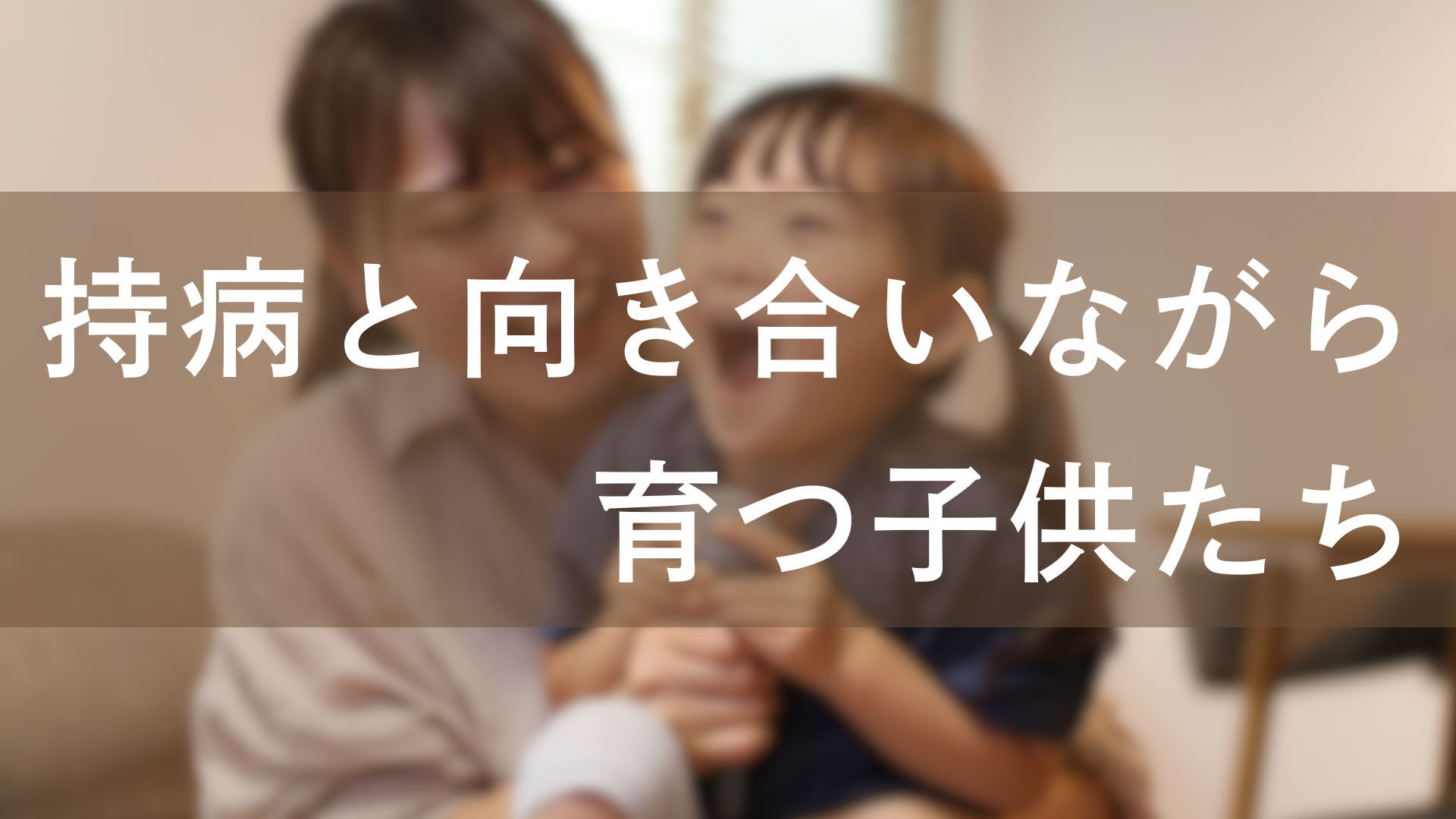
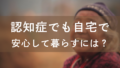
コメント