在宅医療は一人暮らしの方だけではなく、家族と同居している方にも必要になるケースがあります。家族がいるからといって常に万全なケアができるとは限らず、医療的なサポートが求められることもあります。今回は、同居家族がいるにもかかわらず在宅医療を選択したケースをご紹介しますね。
事例紹介:Bさん(82歳・男性)の場合
Bさんは、長男夫婦と同居していました。以前から糖尿病と高血圧を患っていましたが、最近になって脳梗塞を発症。入院治療を受けた後、退院することになりました。しかし、半身麻痺が残り、食事や排泄など日常生活の多くを家族の介助に頼ることになりました。
在宅医療を選んだ理由
Bさんの家族が在宅医療を選択した理由は以下の通りです。
- 家族の介護負担を軽減したい
長男夫婦は共働きで、日中はBさんの世話ができない状況でした。訪問医療や看護のサポートがあれば、家族の負担が軽くなると考えました。 - 住み慣れた自宅で安心して過ごしたい
Bさん自身が「病院ではなく、できるだけ自宅で過ごしたい」という希望を持っていました。 - 医療処置が必要なため
退院後も、褥瘡のケアやリハビリ、糖尿病の管理などの医療的サポートが必要でした。
在宅医療開始後の流れと利用サービス
Bさんの家族は、ケアマネージャーや医師と相談し、以下のような在宅医療の体制を整えました。
- 訪問診療の導入
- かかりつけ医が月に2回自宅を訪問し、全身状態のチェックや薬の処方を行う。
- 必要に応じて血糖値の管理や血圧測定、栄養指導を実施。
- 訪問看護の活用
- 週に2回の訪問看護で、褥瘡の処置、服薬管理、バイタルサインの確認。
- 体調の変化があれば、医師と連携して早期対応。
- 訪問リハビリの併用
- 週1回、理学療法士によるリハビリで、半身麻痺の改善を目指す。
- 自宅内での動作訓練や、転倒予防のアドバイスを受ける。
- 介護サービスの活用
- 介護ヘルパーが週3回訪問し、食事準備や入浴介助をサポート。
- デイサービスを週2回利用し、社会交流の機会を増やす。
- 緊急時対応の確保
- 24時間対応の訪問看護ステーションと契約し、夜間や急変時に対応できる体制を確保。
- 家族と医療チームが連携し、緊急時の対応フローを共有。
在宅医療開始後の変化
在宅医療を開始したことで、Bさんの生活には以下のような変化が見られました。
- 家族の負担が軽減
医療・介護スタッフがサポートすることで、長男夫婦の負担が減り、精神的なゆとりが生まれました。 - Bさん自身がリラックスできる環境を確保
病院と違い、自宅で安心して過ごせることで、表情が明るくなりました。 - 医療的なケアが継続でき、体調が安定
定期的な診察や看護が受けられることで、健康状態の悪化を防ぐことができました。
まとめ
家族がいることで安心できる一方、介護や医療ケアの負担が大きくなることもあります。在宅医療を活用することで、家族の負担を軽減しながら、より良い療養生活を送る選択肢が広がるかもしれません(*^^*)
ご家族の状況に合わせたサポートを検討することで、無理のないケアが実現できるかもしれません。少しでも不安がある方は、医療機関やケアマネージャーに相談してみるのも一つの方法だと思いますので、ぜひ抱え込まずに相談してみてくださいね。
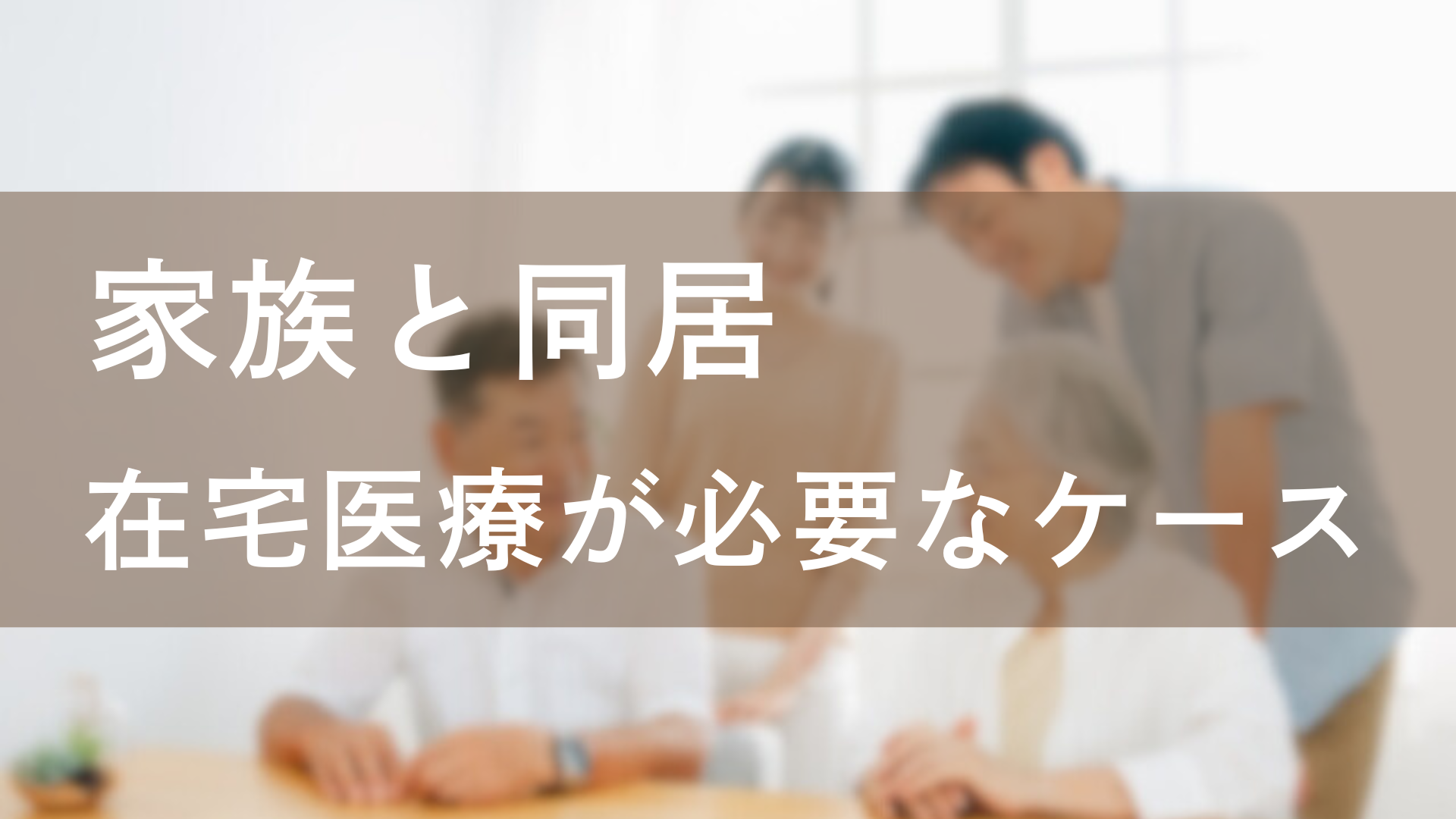
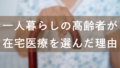
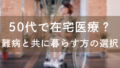
コメント