介護と聞くと、介護する側の負担に注目しがちですが、介護される側にも大きなストレスがあることと思います。日常生活の中で思うように体が動かせなかったり、自分の意思が十分に伝わらなかったりすると、もどかしさや寂しさを感じることもあるかもしれません。さらに、生活環境の変化や人との関わり方の変化によって、心理的な負担が増すことも少なくありません。
本記事では、介護を受ける方が少しでも穏やかに、そして自分らしく生き生きと暮らせるためのヒントをお伝えしていきます。
目次
- 人が生き生きと暮らすための条件
- 介護される側のストレスの主な原因
- 介護される側のストレス対策
本文
1.人が生き生きと暮らすための条件
どんな人でも、充実した生活を送るためには、以下のような要素が必要です。
- 自己決定感
物事を自分で選び、決められること。 - 社会とのつながり
家族や友人との交流を持ち、社会の中で役割を感じること。 - 身体的・精神的な健康
適度な運動や趣味、楽しみを持つこと。 - 安全・安心な環境
住み慣れた環境の中で、信頼できる人と暮らすこと。
これらの要素が崩れると、人はストレスを感じやすくなるかもしれません。
2.介護される側のストレスの主な原因
自立できないことへの喪失感
これまで自由に行動できていたのに、身体機能の低下や病気により、今までできていたことができなくなると、自分の存在価値を見失うことがあります。「人に頼らなければならない」という現実は、大きな精神的負担となり、自尊心が低下する要因になります。また、「昔はできていたのに」という思いが強くなると、抑うつ状態になることもあります。
介護者への負担を気にする
介護は家族や介護スタッフに大きな負担をかけるため、介護される側が「迷惑をかけている」と感じることが多くあります。特に家族介護の場合、介護者が疲弊している様子を目の当たりにすると、罪悪感や無力感を抱き、ストレスにつながることがあります。また、介護者との関係が悪化すると、気を使いすぎてしまい、精神的な負担がさらに増すこともあります。
プライバシーの喪失
入浴、排泄、着替えといったプライベートな行動を他者に手伝ってもらうことは、多くの人にとって大きな抵抗を伴います。特に、異性の介護者に介助される場合には羞恥心が強くなり、強いストレスを感じることがあります。また、介護施設に入所した場合、他の入居者や職員との関係の中で自分のプライバシーが守られないと感じることもあり、ストレスの原因となります。
孤独感や社会的なつながりの減少
高齢になると、外出する機会が減り、交友関係が狭まることが多くなります。これにより、社会とのつながりが希薄になり、孤独感が強まります。特に、家族と離れて暮らしている場合や、配偶者を亡くした後は、話し相手が少なくなり、精神的に不安定になることがあります。また、身体の不自由さから外出を諦めると、ますます社会とのつながりが途絶えてしまい、孤独感が増してしまいます。
介護環境の変化や人間関係のストレス
介護が必要になると、自宅から介護施設へ移ることもあり、住環境が大きく変わることがあります。慣れ親しんだ場所を離れることで、精神的に不安を感じることが多く、適応するのに時間がかかることがあります。また、新しい介護者や他の入居者との人間関係にストレスを感じることもあり、生活環境の変化が心理的負担となることも少なくありません。
3.介護される側のストレス対策
できることは自分で行う
すべてを介護者に任せるのではなく、可能な範囲で自分で行うことで、自尊心の維持につながります。生活動作の全てではなく、一部分(例えば着替えをする際も、ズボンは介助してもらうけど服の袖通しは自分で行う、など)だけでもやれることを増やしていくことも良いかもしれません。
コミュニケーションを大切にする
介護者との信頼関係を築くことで、精神的な安定が得られます。感謝の気持ちを伝え合うことも重要です。近い存在であるがゆえに、いざとなると言葉にできないときもあるかもしれませんが…。思っているだけでなく、伝えることは現場をまわっていてもとても大切と感じることが多くあります。
趣味や楽しみを見つける
読書や音楽、簡単な運動など、楽しめることを見つけると、生活に張りが生まれます。忘れかけていたけれど、昔聴いていた好きな音楽を聴いてみたりするだけでも、自分の『好き』に触れて気持ちが紛れることもあるかもしれません。
介護サービスを活用する
デイサービスや訪問介護を利用することで、介護者の負担を軽減し、介護される側のストレスも和らげることができます。家族である介護者を気遣うがあまり、気疲れしてしまう方にとっては、介護をすることを職業とする専門家にのほうがお願いしやすい面もあるかもしれません。また、介護者には言えないストレスを、第三者には話せるということもあるかもしれません。傾聴も業務のひとつとしてあるので、遠慮なくお話してみてくださいね。
社会とのつながりを持つ
オンラインや地域の交流会などを活用して、社会との関わりを継続することが大切です。また、デイサービスなどで同じ境遇の方とお話をしたり、スタッフとともにアクティビティに取り組むことも、人との繋がりを持てて良いかもしれません。
まとめ
介護は「する側」だけでなく、「される側」にとっても大きな課題です。介護される側の方々が少しでも前向きな気持ちで過ごせるよう、周囲の理解と適切な支援が必要となります。介護される方の気持ちに寄り添い、負担を軽減するための工夫を少しでも取り入れていけると良いかもしれませんね。
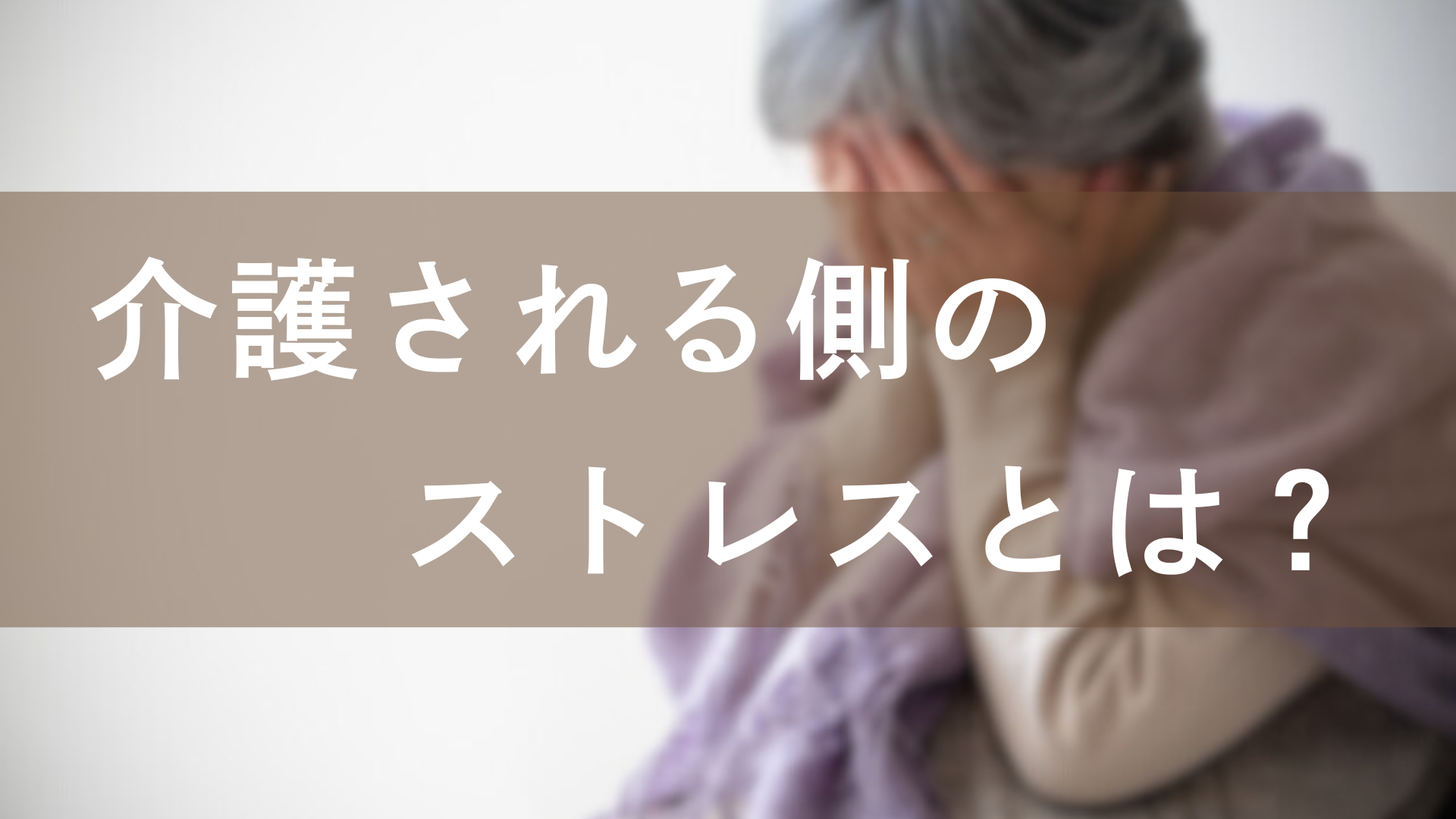
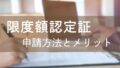
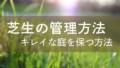
コメント